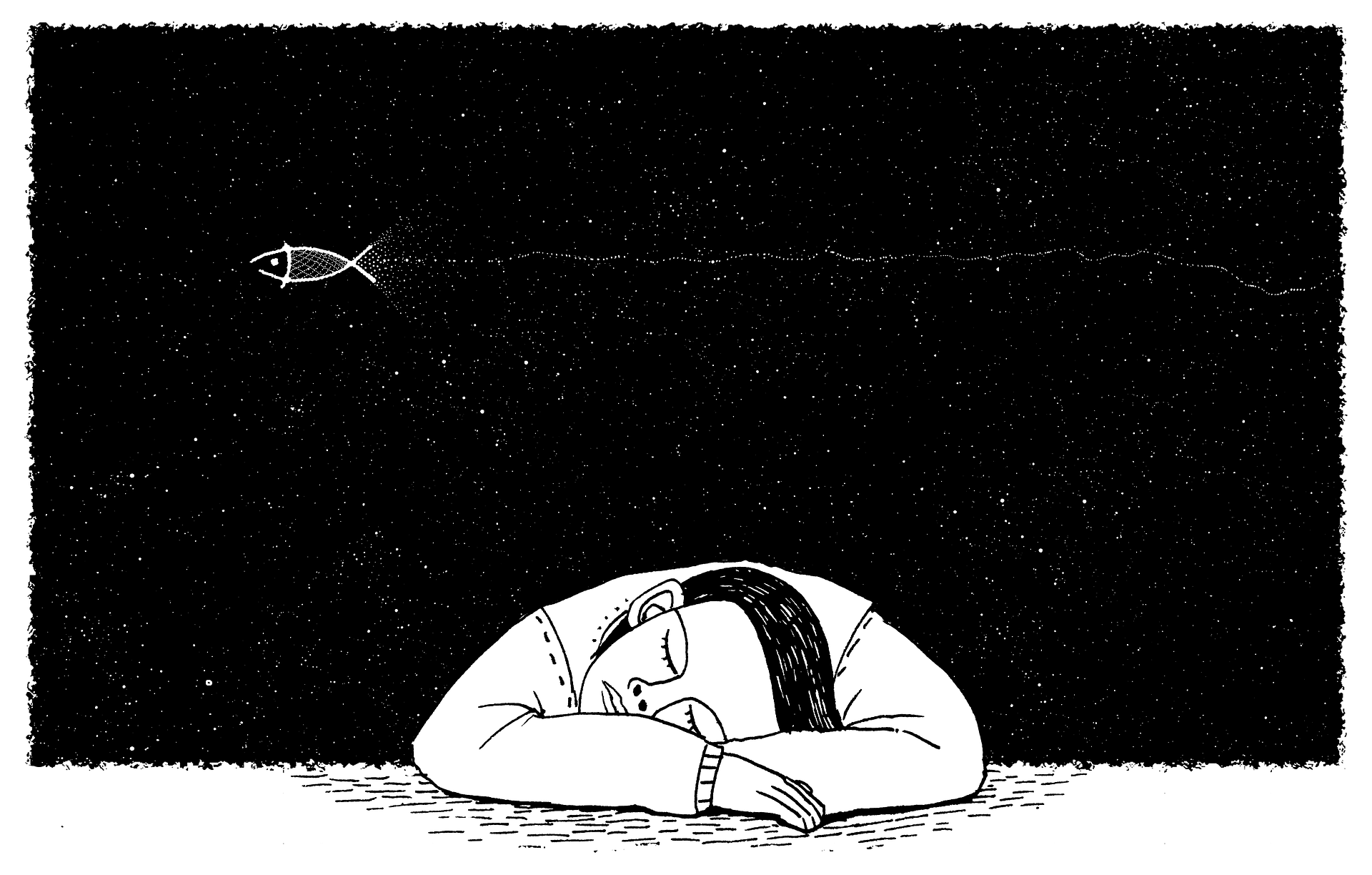何のために音楽をやるのか?
何のために、あるいは、何を目的として?
…というのを考えないと行き詰まる、と、常々思っている。
親の期待に応えるため。
お金儲けをするため。
好きだから。
とにかく表現がしたい。
音楽業界に風穴を開けたい。
まあでも、トヨタ式に考えるとそれら全てに対して「なぜ? 何のため?」と続けられるのだけども、とりあえず今回はやめておこう。長くなるし。
音楽の持ち主は誰か?
Twitterで、曲は作曲者の持ち物なのか、みたいな議題が上がったことがあった。
より正確に言うと、「演奏者は作曲者が書いたとおりに演奏すべき」といった感じの旨。
いろいろ意見が飛んだ。全部は見切れていない。
私の意見はちょっととがっている。
音楽(その曲)の持ち主は作曲者ではない。
音楽の神様、つまり、音楽という概念それ自体が持ち主である。
私の持ち主は私。
音楽の持ち主は音楽。
そういうことなのだと感じた。
作曲家も、演奏家も、指揮者も、聴衆も、たかが人間である。
人間が音楽を我が物顔で扱っていること自体が馬鹿げている。
…といった、古風な考え方をまついはする。
音楽は私の道具ではない
とある演奏を袖で聴いていた。
あれはストラヴィンスキーの火の鳥だったと思う。
稲妻が走った。
私は、それまで、音楽をツールとして考えていた。
何のツールかというと、自己表現のためのツールである。
そう考える人は少なくないだろう。
だが、そのとき私は悟った。
音楽は私の道具ではない。
私が音楽の道具なのだ。
音楽というクラウドを通して、私は作曲させられている。
自分の意思で作曲しているというのは大きな勘違いで、音楽が私に曲を書かせているのだ。
そう気づいたとき、いろいろ腑に落ちた。
人間が、音楽のことをあーでもないこーでもないと議論するのが非常に馬鹿げているように思えた。
もっとも、馬鹿げているのが人間なのだから、それを否定はしない。
私だってすこぶる馬鹿げている。
音楽が何を求めているか
自分が作曲しているわけではないと感じたとき、いわば自分は音楽が用いる箸みたいなものだから、使用者が、つまり音楽が私に何を求めているか感じるようになった。
箸を開く。ものをつかむ。口に運ぶ。
自分が曲を書くとき、そういう一連の流れを…流れというと語弊があるのだが、要するに使用者たる音楽が何を求めているのか、すなわち、自分が書いている曲について音楽が何を求めているのか、できるだけ感じようとするようになった。
つまり、行き先というか。音楽の行く末というか。
けれど、それは多くの作曲家が、同意するところではないか?
音楽が、その曲が行きたい場所は、音楽が決める。曲の行き先は曲が決めるのであって、作曲家が決めることではないのだ。
そういえば…小説もそういう感覚で書いていたな。
小説の場合は、キャラが自分で行き先を決めていたけど。
いずれにせよ、私が余計なお節介をする必要性を感じないのだ。
お供えする
冒頭の問いに戻る。
何のために音楽をやるのか? 特に、作曲をするのか?
いろいろ考えたが、自分の思いとしては、「音楽の神様にお供えするため」というのが近い気がする。
急に日本風の考え方になったが…
私は日本生まれの日本育ちの日本人だし、日本っぽくなっても不思議はない。
収穫祭にお供え物をするように。
音楽の神様に「みてみてー!」って、曲をお供えしたいのだ。
こんなに大きくなりました、って。
今書いてる曲は…どんな風に育つだろうか。
とても、楽しみである。